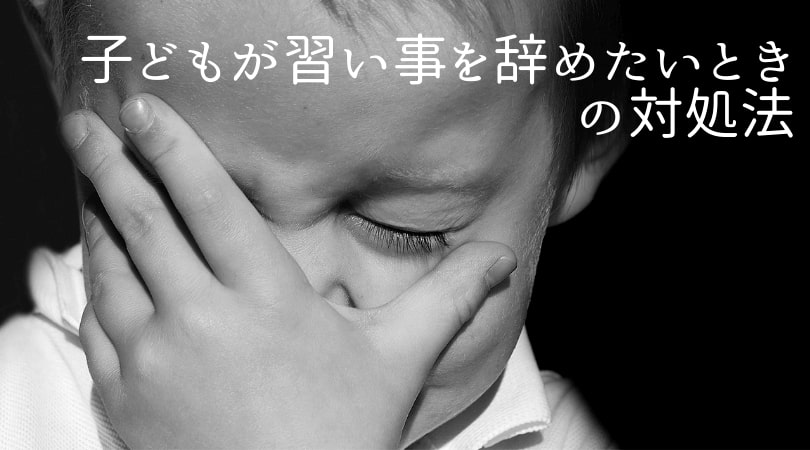そろばんでやる気を出す方法【伸びない一番の原因はやる気のないこと】
習い事のランクインでも見かけるのが「そろばん」。
上位ではないけど、必ず目にしますよね。
 なまず博士
なまず博士計算力や右脳の活性化だったりと、脳みその運動として人気高い習い事じゃな
でもこんな状態だと…
せっかくならっているのに級が上がらない…
まったくやる気がなくて、ただ通っている状態…



頑張ってほしいけど、級も上がらず効果もないなら辞めようか、と悩んでいる方、この記事をみてもう一度検討してみてください。
なぜなら、あなた次第でお子さんが大きく成長する可能性があるからです。
結論からお伝えしますと、
そろばんはお子さんのやる気と親の戦法次第でものすごく伸びる習い事です
やる気さえあれば自然と級は上がっていきます





そうですね、当然です。ではなぜやる気がないのか?
考えられる原因はこちらの中にありませんか?
◆反復するのが好きではない
◆そろばんが好きではない
◆級がなかなか上がらない(同じことばかりやっていて飽きた)
◆周りの子と比べられるのが嫌だ
◆先生が好きではない
◆宿題も嫌だ
色々あると思いますが、こんなところでしょうか。
突然ですが佐藤ママご存知でしょうか?
4人のお子さんを全力でサポートしてお子さん全員を東大の最難関理Ⅲに入学させるという、あの偉業を成し遂げた佐藤ママです。



お子様自身の努力ももちろんありますが、佐藤ママなくしては達成できなかったことであって、佐藤ママ自体もそのように仰っています。
佐藤ママの「こどもをサポートする」姿勢をあなたにもマネしてほしいのです。
さきほどのやる気が出ない原因、それを紐解いてサポートしていくことが必須です。



要は親のマネジメント次第でそろばんもグッと伸びるんじゃな
幼い子こそ親の手助けが必要
幼児からそろばんをやっている子もいますが、ここではわかりやすく小学生を例にしますね。
小学生は学校も自分で行って帰ってくる。宿題もするし、お友達と遊ぶ約束も取り付け、外出もする。
とにかくできることが幼児に比べて増えていますが、まだまだこどもなんです。
なので、「そろばんの宿題をきちんとやりなさい」「復習しなさい」と言って勝手にやる子なんて少数派です。
親の関わりが重要
★スケジュールを管理
★声をかけてあげる等
やる気がでない状態でずっといさせること、これがなにより意味のないことになってしまいます。
間違えても怒らない
そろばんに限らず、たとえば学校の宿題でも言えること。
「間違ってるよ!直さなきゃ!」なんて言ってはダメです。
そもそも、勉強を自らやっているという状態はほめられることです。



ほめられることをしているのに、答えが間違っていたら怒るのはおかしいんじゃよ
勉強の対する姿勢がよくなかったり、明らかに集中力にかけている時は、
「今は集中していないみたいだから、すこし休んだら?」といってあげることも大事です。
とにかく大げさにほめましょう【視覚的にもほめる】



こどもって、ほめられたいんです。
大人になってもほめられると嬉しいですよね。
- そろばんの宿題を自らしようとした
- 毎日そろばんを触った(少しでも解いた)
- 姿勢がきれい
- 癇癪起こさず最後までがんばれた
自宅でそろばんを復習なり宿題なりをしたときには、盛大に褒めましょう!
そして、検定に受かると賞状をもらってきますよね。
賞状はリビングの目につくところに飾りましょう!



そろばんをしている写真を飾るのもおススメ🧡
ほめる方法には色々あって「ほめ写」もオススメですよ〜


「お母さんにほめられた!私(ぼく)って偉いんだ!」
という積み重ねがやる気をだしますし、なにより自己肯定感を高めることができます。
ただ、ここでほめ方にもポイントがあります。
検定結果や小テストの結果ではなくプロセスをほめる
ほめて伸ばす 【結果ではなくプロセスをほめる】





結果ではなくそれまでの工程、つまりプロセスをほめることが大事じゃ!
というのも、多くの心理学者や教育者の研究で結果がでているのです。
下記どちらをほめることが多いでしょうか?
| A | B |
|---|---|
| ✔️点数をほめる ✔️「頭がいいね〜!」 ✔️「一等賞すごいねー!」 | ✔️テストへの取り組みをほめる ✔️努力をほめる ✔️練習をほめる |



うっかり言ってしまうのはAが多くないですか?
Aは目に見えやすいこともあり、こちらをほめてしまう人多いと思います。
結果をほめるにしても、かならずそれまでのプロセスをほめてください。



なんで?100点や一等賞をほめるだけじゃダメ?
プロセスをきちんとほめてもらえた子は「努力によって知性や学力がつく」と考えるようになります。
やればやるほど伸びる、という風に考えます。そのため、失敗を恐れずに挑戦し、挫折した時は、もっと時間と努力を積み重ねれば乗り越えられる!と思うんですね。
繰り返しになりますが、結果だけをほめるのはやめて、工程や頑張りをほめましょう😉
詳しくはこちらの記事で書いています。


そろばん塾にまかせきりにしない



塾に任せきりはダメじゃ!塾にいった日は教材でどこをやったかチェックしたり、本人にもなにをしたのか聞くことが重要じゃ
正直、時間ない時は面倒です。
こどもが何をやっているのか、どんな難易度の問題をしているのかは把握は必須です。
たまに「うちは先生にお任せしているだけで大丈夫で、家でなにもしなくていいから楽ちんなの~」という方います。
待ってください、先生に「自宅では何もやらなくていいですよ」って言われても鵜呑みは危険です。
任せっきりにしていて、のちにやる気がなくなって、級もあがりにくくなることを想像してください。
幼児さんですごくデキル子いますよね?
あれはお子さん自身もですが、お母さんお父さんも協力しているからです
天才児というのは本当に稀です
デキル子の裏にはかならず「努力」があるのです。
頻度や教室の検討
週に1回、週に2~3回、週5回、と頻度は様々ですよね。
そろばんって反復と、どれだけそろばんにさわっていたかで成果がまるで変わります。
なので当然、頻度が高い方が身に付きます。
かといって、頻度を高くすることでもしかしららモチベーションが下がっている可能性もありますので、ご注意ください。
やる気がないお子さんの場合、もしかした頻度を変えてみると好転するかもしれません。
◆週1回→つまらない
週3回に変更したら、自分でもわかるくらいに成長をして楽しくなった!
◆週5回→毎日そろばん嫌だ
週2回に変更したら、他のこともできる。しかも毎日いつもしていたおかげで自宅学習で賄える
教室も、「やさしい女性の先生」や「無口そうな初老の男性」とでは、向いている子がわかれます。
やさしい先生はそれこそやる気を引き出してくれますし、ちょっと怖そうな先生はいい緊張感を生み出してくれます。
お子さんに合ったタイプの先生や教室を検討し直すのも手です
先生とも情報の風通しをよくする
そろばん塾との先生とは風通しはいいですか?



とはいえ、送迎していない場合はなかなか会って話すことも難しいですね。
なにより先生が他のお子さんを教えている最中はもちろん中断できません。
私事ですが、息子の通っているそろばん教室は先生が親との交流を大事にしてくださっている方でした。
こちらから話題を振ることは先生もお忙しいので極力やめていますが、先生から自宅での学習方法や、塾でこれからやっていくことや、検定の予定(〇〇月には珠算〇級を受けて、その次は暗算の〇級をどうですか?)まで網羅していて教えてくださいます。



しかも、この先生は親さえもほめてくれるんですよ!
👩「お母さんの助力があってこその成果です!」(先生…好きイイイ!)
そんな感じなので、他のお子さんも息子も先生が大好きです。
もしコミュニケーションが図れる機会があれば、先生に相談してみましょう。
そろばんを家でやることをルーティン化(習慣付ける)
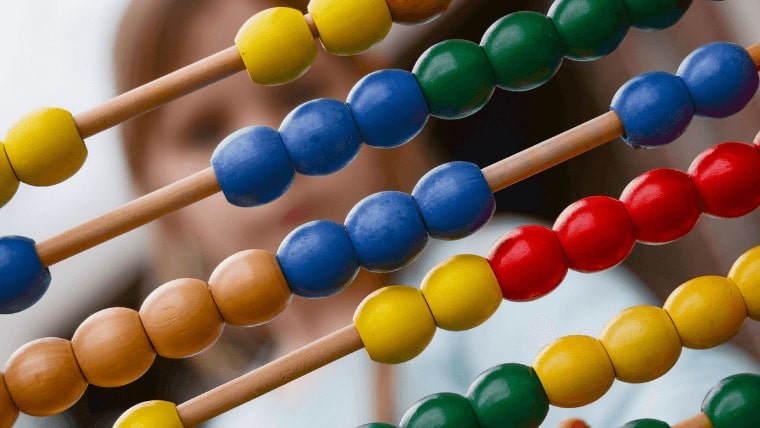
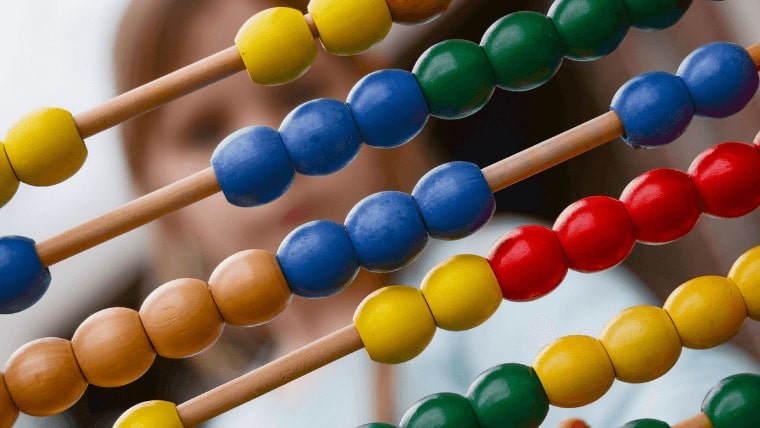
さきほどそろばん塾にまかせきりはだめ、自宅でも対応を!って言いました。



簡単なことからやってみましょ😉
内容もですが、なにより大事なのはそれを習慣付けること
いきなり毎日できなくてもいい
毎日そろばんをしている子の方が伸び率はいいです。これは当たり前です。
他の習い事にも共通していますが、たとえばピアノ。
毎日練習する子と、レッスンだけで練習する子。
後者の子のが上手なのは当たり前です。なので、最初は自宅ですることを習慣付けましょう。



見取り算5問とかからはじめてみましょ♪
ハードルは低くから設定です。お子さんも5問程度なら「じゃあやろっかな」となるはずです。
見取り算5問×1週間で、35問できます。1日で35問解くより効果的です。



最初は3日に1回とかでもいいゾ。とにかくスモールステップじゃ!
やる気は親のサポート次第で上昇する【まとめ】
やる気がでないお子さんはそろばんのモチベーションが低いです。
↓
そこを上げてあげると、ぐっと伸びます。
↓
そのためには、親のサポートが必要になります。
↓
尻を叩くやり方ではなく、ほめて伸ばすというやり方です。
↓
環境や先生にお子さんが合っているのかどうか、見直すことも重要です。
↓
毎日そろばんをやることが習慣化できてしまえば、モチベーションも自然とアップします。



やる気さえ出せばそろばんは伸びてきます🧡
やる気を出させるのは親の仕事ではないでしょうか?
お金を払っているのだから、塾の仕事でしょう、という意見もあるかと思います。
ただ、習い事の先生と親とでは子供に対する想いは当然違います。触れ合う時間も異なります。
「結果にコミットする」ライザップの有名なキャッチコピーがありますが、まさしく教育も親がコミットすれば子供の結果がみえます
できることからはじめましょう♪